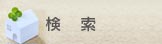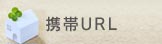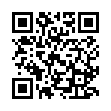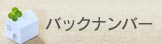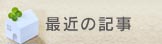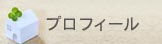暑いですね。昨日終了した6月定例県議会の後処理のため、県議会の控室に出てきていますが、頭から水をかぶりたいような暑さです。デスクの横で最近離れられない(離れたくない?)パートナーとなった扇風機が奮闘中です。
暑いですね。昨日終了した6月定例県議会の後処理のため、県議会の控室に出てきていますが、頭から水をかぶりたいような暑さです。デスクの横で最近離れられない(離れたくない?)パートナーとなった扇風機が奮闘中です。
私にとって初めての本格的な議会だった6月定例議会。初めての一般質問に、初めての予算審議、初めての起立採決とまさに「初めて」づくしでしたが、記者時代とは議会を見る目も少しずつ変わってきました。決してそこに染まってしまったという意味ではなく、見えなかったものも見えてきたということです。
たとえば、課題を見つけ出し、相手の見解を問う「質問」という同じ作業でも、基本的に記事を書くための記者の質問と、今後の方向性に直接関わる議員の質問というのは、やはり少し種類の違うものです。
一概には言えませんが、質問は記者でも議員でも、客観的なデータや状況を積み上げたうえで、相手の認識を問うのが基本的な形でしょう。しかし議員の場合は、その中に自らの主張を明確に織り交ぜることになります。有権者の信任を得て、議場にいる以上「私はこう思う」ということを主張しなければ、存在意義は薄れてしまうわけです。
私はメディアにももう少しそういう面があっていいと思っています。ただ「客観性」「中立性」という極めて重要だけれども、時に身動きが取れなくなる縛りの中で、苦しんでいるような気がします。
 政治メディアの中では「党内には・・・・・・という声がありますが、いかがか?」とか「与党(野党)内には・・・・・の動きが高まる気配があるが、どう考えるか?」というような質問がよくあります。大方の場合、そういう聞き方をする場合は、その政治家に否定的な趣旨で質問していることが大半です。
政治メディアの中では「党内には・・・・・・という声がありますが、いかがか?」とか「与党(野党)内には・・・・・の動きが高まる気配があるが、どう考えるか?」というような質問がよくあります。大方の場合、そういう聞き方をする場合は、その政治家に否定的な趣旨で質問していることが大半です。
そういう問いに政治家がどう応えるかで「言葉」以上の反応を見るという要素もあります。むきになって反論することもあれば、「私は聞いたことがありません」と受け流すこともあるわけで、その反応は時に言葉そのものよりも象徴的だったりします。だから取材手法としては有効なわけですが、やはりちょっと聞き手はずるいなと感じます。顔の見えない誰か(党内にはとか、与党内には・・っという風に)の発言を基にすることで、自分の立ち位置を示す必要がないので、記者としては楽な質問なのも事実です。こんなことを言っていると、昔の仲間たちから怒られるかもしれません。もちろん私もその一員だったわけで、反省と自戒を込めての感想と受け止めてください。
記者時代に担当していたある政治家が、先ほど例示したような質問をすると、「だったら君はどうすべきだと考えるんだ?」「自分の考えも示さずに質問するな」と恐い顔をされることがよくありました。当時は「そんなの立場が違うじゃないか」と思うことも少なくありませんでしたが、反面、自らの主張をすることに臆病なことを感じていたのも事実です。
話が大きく逸れてしまいましたが、閑話休題。
最初に言おうとしていたのは、議員としての質問は、考えを問う場であると同時に、自らの主張の場ということです。本会議場での質問もそうですし、委員会審議も同じです。そういう意味では、もちろん発言の責任も重いわけですが、先に述べたような記者時代の「遠慮」はなく、自らの考えを口にできる「伸びやかさ」のようなものをこの議会中に感じていました。
だからこそ、主張の仕方、つまり質問の仕方は様々あっていいわけです。正攻法でどんとぶつかっていく方法もあれば、搦め手で攻める老練なやり方もあるのでしょう。興味深く他議員の発言、質問も聞きながら、多くを学んだ6月議会でした。
【渡辺創】
※写真は、“夏”の県庁と、県庁前庭の一コマ